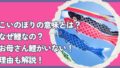子供とのおでかけは楽しいですよね!
テーマパークや旅行など、いろんな場所に行くとき、料金を確認するときに、戸惑うことがありますよね。
それは、「小学生以下」という表現です。
例えば、「小学生未満」「小学生以上」「未就学児」「幼児」「小人」など、いろんな言い方がありますが、実際には何歳から何歳までを指しているのか、ご存知ですか?
特に「小学生以下無料!」と書かれている場合、無料かどうかは重要ですよね?きちんとした理解がトラブルを避けるポイントです。
そこで今回は、これらの違いについて詳しく調べてみました。
小学生以下とは何歳まで?年齢別のわかりやすい解説!
子供とのお出かけやイベント参加の際、年齢制限や料金の割引など、知らないと損をすることがありますよね。
そこで気になるのが、「小学生以下」とは具体的に何歳から何歳までを指すのか、ですね。
たとえば、楽天トラベルには「子供無料」のプランがあることもありますが、この「小学生以下」とは一体何歳までを指しているのでしょうか?理解しておかないと、お得な旅行プランを逃してしまうかもしれませんね。
実際の答えは、0歳から小学6年生(12歳)までです。
つまり、赤ちゃんから小学校6年生までが「小学生以下」に含まれます。ただし、12歳を超えた瞬間からは「小学生以下」の対象外となるので、注意が必要です。
また、「未満」という表現もよく見かけますね。これは、指定された基準の下限よりも年齢が少ないことを意味します。
例えば、「小学生未満」とは、小学校1年生(6歳)よりも年齢が下のことを指します。つまり、0歳から5歳までが該当します。
この「未満」という言葉も、料金やサービスの対象範囲を理解する上で重要なポイントです。
年齢別呼び方のまとめ表!小学生以上、以下、未満一覧表
| 呼び方 | 年齢 | ポイント |
|---|---|---|
| 小学生以下 | 0~12歳(小学6年生を含む) | 12歳でも中学生は✖ |
| 小学生以上 | 6歳(小学1年生)~大人まで | 6歳でも保育園・幼稚園児は✖ |
| 小学生未満 | 0歳~6歳(小学校入学前の子) | 6歳でも小学1年生は✖ |
| 未就学児 | 0歳~6歳(小学校入学前の子) | 6歳でも小学1年生は✖ |
| 幼児 | 1歳~6歳(小学校入学前の子) | 6歳でも小学1年生は✖ |
| 乳児 | 0歳~1歳くらいまで | |
| 乳幼児 | 0歳~6歳(小学校入学前の子) |
表を見ると、「以上」「以下」「未満」がややこしいですよね(;^_^A) これらのポイントをしっかり押さえておくことが重要です!
では、さらに「小学生以上」を詳しく説明しますね。
小学生以上とは?
小学生以上とは、具体的に何歳から何歳までを指すのでしょうか?
答えは、小学1年生(6歳)から大人までです。
例えば、小学生以上のイベントには、幼稚園児や保育園児は参加できないことがあります。また、学生割引がある場合も、小学生以上が対象となることがよくあります。
同様に、「以上」という表現は、指定された年齢を含むことを意味します。したがって、小学生以上は小学1年生よりも上の年齢の人々を含みます。
次に、未満との違いについて説明します。
小学生未満とは?
小学生未満とは、具体的に何歳から何歳までを指すのでしょうか?
答えは、0歳から小学校入学前の子(6歳)までです。
未満とは、指定された数を含まず、その数よりも小さいことを意味します。例えば、10未満ならば、10よりも小さく、10は含まれません。
つまり、小学生未満は小学1年生を含まない、それよりも下の子供たちを指します。つまり、小学校に入学していない子供たちということになります。
具体的な例を挙げると、保育園や幼稚園に通っている子供たちが小学生未満に該当します。また、公共施設やイベントにおいて、小学生未満の子供は保護者の同伴が必要な場合があります。
他にも、同様の意味を持つ表現として未就学児があります。
未就学児とは
未就学児とは、具体的に何歳から何歳までを指すのでしょうか?
答えは、0歳から小学校入学前の子(6歳)までです。
未就学児とは、小学校などの初等教育機関に就学する年齢(学齢)に満たない児童のことを指します。
つまり、未就学児は小学校に入学していない、未就学の子供たちを指します。これは、「小学生未満」と同じ意味ですね。
他にも、よく聞く「幼児」はどうでしょうか?
幼児とは、具体的に何歳から何歳まで?
幼児とは、具体的に何歳から何歳までを指すのでしょうか?
答えは、1歳から小学校入学前の子(6歳)までです。
幼児とは、一般的には幼い子供を指しますが、法律上では1歳から小学校に入学するまでの子供を指します。
具体的な定義としては、児童福祉法では、幼児は1歳から小学校に就学するまでの子供を指します。
ちなみに、幼児に類似した言葉として、「孩児」「緑児」「嬰児」「やや稚児」などがあります。
では、さらに小さい子供を指すのは乳児と言いますが、この表現はどのような範囲を指すのでしょうか?
では乳児とは何歳のこと?
乳児とは、具体的に何歳から何歳までを指すのでしょうか?
答えは、0歳から1歳くらいまでです。
乳児とは、生後1年くらいまでの小児で、乳で育てられ、歩き出すまでの時期の子供を指します。
ちなみに、生後28日未満の子供は「新生児」とも呼ばれます。
そして、「乳児」と「幼児」を合わせた言葉、「乳幼児」は0歳から6歳くらいまでの未就学児のことを指します。ただ、確かに「未就学児」という言葉で十分ですね。
それにしても、子供についての細かい年齢別の呼び名に驚きましたね。
次は、さらに大きな分類である「小人」について調べてみました。
小人の読み方は?何歳から何歳まで?
小人とは、具体的に何歳から何歳までを指すのでしょうか?
答えは、施設によって定めが異なります!
ちなみに、「小人=しょうにん」と呼ぶことをご存知でしたか?私はずっと「こびと」と思っていました(ノД`)・゜・。
料金区分などでよく使用される「小人」は、施設によって年齢区分が異なります。
例えば、東京ディズニーリゾートでは以下のような区分があります:
- 大人:18歳以上(※1)
- 中人(中学・高校生):12~17歳(※2)
- 小人(幼児・小学生):4~11歳
※1)18歳の高校3年生は、高校を卒業する年の3月末まで中人料金が適用されます。 ※2)12歳の小学6年生は、小学校を卒業する年の3月末まで小人料金が適用されます。
また、イオンシネマでは次のような区分があります:
- 一般:1,800円
- 大学生:1,500円
- 高校生:1,000円
- 小人 ※3 ※3歳以上、中学生以下:1,000円
同じ「小人」でも、対象年齢が施設によって異なります。年齢を正確に確認することが重要ですね!
それでは、一般的に「子ども」と呼ぶ年齢の範囲や、「児童」という用語の意味について説明します。
子ども・児童は具体的に何歳から何歳まで?
子ども・児童とは具体的に何歳から何歳までを指すのでしょうか?
答えは、法令によって異なります!
例えば、児童福祉法では「児童」を18歳未満と定義しています。一方、子ども・子育て支援法では「子ども」を18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供と定義しており、つまり高校生までを指します。
したがって、法律によって、子どもや児童の定義は異なることに注意する必要があります!
銭湯に異性が入れる年齢
ちなみに、銭湯で異性が入ることのできる年齢についてですが、これもやはり法律や地域によって異なります。
例えば、一部の銭湯では、小学校低学年からでも異性の入浴が認められることがあります。しかし、その他の銭湯では、中学生以上から異性が入ることを許可する場合もあります。
また、特定の時間帯や特別なイベントでは、幼児や未就学児でも家族と一緒に入浴できる場合もあります。ですから、銭湯に行く際は、事前にルールや規則を確認することが重要ですね。
【子供の年齢別区分を正しく理解しよう!】
子供という言葉には、実は法律や施設によって異なる定義があります。まず、「小人」という言葉に驚きますが、施設によっては年齢区分が全然異なります。
例えば、東京ディズニーリゾートでは大人、中人、小人という年齢区分があり、年齢ごとに料金が異なります。
一方、イオンシネマでは一般や学生、そして小人料金が適用されますが、その年齢範囲も違います。
また、「子ども」や「児童」という言葉も法律で定められています。児童福祉法では18歳未満が児童と定義され、子ども・子育て支援法では18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供が子どもとされています。
つまり、子供の年齢別区分は様々であり、法律や施設の定めによって異なることを理解する必要があります。これを知ることで、イベントや施設の料金体系を理解し、節約や計画立てに役立てることができます。